CSRは欧米では1990年代後半から本格化し、日本でも「CSR元年」と呼ばれる2003年ごろから企業の取り組みが活発になっている。日本において約5年を経た今、頻発する企業不祥事や世界的な経済不安を受け、改めて「CSRとは何か?」が問われているのかもしれない。一橋大学大学院商学研究科教授、谷本寛治氏に、CSRの定義や最近の動向などについて聞いた。
基本をなおざりにしないことがCSR
 谷本寛治氏
谷本寛治氏
── CSRの定義を解説してください。
メーカーを例にすると、安い物を提供さえしていればいい、法令を順守しない、環境に負荷をかける、女性を評価しない、障がい者を排除する、途上国の労働環境や人権を侵害する、さらにこうした負の情報を開示しない……といった問題を起こさないよう手段を講じていくことです。さもなければ、市場や社会の信頼を失い、企業として存続することは不可能です。つまり、社会やステークホルダーに対する責任を果たすことは「企業経営のあり方そのもの」である。私は、狭義においてCSRをそう定義しています(次ページ図)。
さらに、環境配慮型、障がい者支援型の商品やサービスを開発するなどの「社会的事業」や、寄付やボランティアなど本業の経営資源を活用した支援活動である「社会貢献活動」も、広い意味ではCSRに含まれます。企業に期待される役割が広がっている今、いずれも意義ある取り組みです。とはいえ、CSRの基本はあくまで経営のあり方そのもので、その基本をなおざりにして、社会的事業や社会貢献活動をしたところで「CSRを果たしている」と評価されるものではありません。
── 世界的に見たCSRの動きは。
ホットな話題の一つは、組織の社会的責任に関するISO26000の規格化です。2004年のISO/SR国際会議で決定し、10年に本格始動する見込みです。ISO26000では「社会的責任」を、①環境②組織のガバナンス③公正な事業活動④人権⑤労働慣行⑥消費者課題⑦コミュニティー参画/社会開発の7項目に分けています。
環境マネジメントシステムに関する国際規格ISO14001とは違い、ISO26000は取得に関して第三者認証を必要とはしない、規格としては最もゆるい「ガイダンス」で、企業のみならずあらゆる組織を対象にしています。ただこれまでの決め方と違い、ごく一部の先進国の専門家だけでなく、発展途上国やNGOなど、幅広いステークホルダーが同じテーブルにつき議論と策定が進められてきました。ISO26000は、おそらくこれまでのものとは異なる重みを持つでしょう。今後、グローバルにビジネスを進める企業は、避けては通れない重要な規格になるだろう、と見ています。
対応の進展を契機に社内での議論が活発化
── 日本におけるCSRの動向は。
CSRというブームが広がってきて約5年がたち、かなり理解は定着しつつあります。CSRの部署を設けたり、担当役員を置いたりするなど、制度的な対応は進んでいます。CSR報告書を作る企業も国内で1,000社以上を数えるようになったといいます。しかし、日本では横並び意識が強いため、「あそこの会社がやっているから」という理由で、部署や報告書を作る企業が少なくありません。
CSR報告書は、いわば非財務の年次事業報告書で、財務報告書と対になるものです。財務報告書から見えてこない、環境問題や社会問題への取り組みや成果を、達成できたこともできなかったことも含め開示していくことは、1年間の経営そのものを明らかにすることになります。CSR報告書は、コーポレートコミュニケーションの視点から見ても、非常に重要な役割を持っているのです。ただ現状は、中期経営計画の中にきちんとCSRをうたい、部署ごとの年次アクションプランに落とし込まれているものもあれば、会社案内と大差がないようなものも見られる。まさに玉石混交といえます。
しかし、たとえ最初は形から入ったCSR報告書作りでも、担当者がきちんと作ろうと動けば、社内論議が活発になる。すると、形を整えるプロセスを通して、CSRへの理解も定着してきます。欧州のように「こうあるべきだ」という理念から入るのとは違い、形から入って、現場から議論を広げながら自分たちに合ったものに作り上げていくのは、日本的なスタイルなのかもしれません。
海外の「厳しい目」に迫られる対応
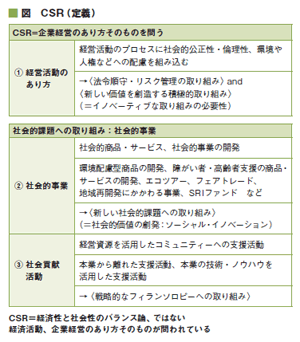
── グローバリゼーションがますます進んでいます。日本企業のCSRの取り組みに与える影響は。
ステークホルダーとの関係性が大きく変わってきていることは確かです。かつての日本企業では、株主や取引先、そして従業員も企業というシステムに組み込まれていて、ステークホルダーが企業に対して「物申す」風潮はほとんどありませんでした。株主も、グループ内の金融機関が中心で相互持ち合い関係にあって、株主総会では「うちも何も言わないから、そちらも何も言わない」という暗黙の了解がありました。
ところが、90年代にバブルがはじけ、外国の機関投資家が増え、経営者の指名や経営戦略、経営者の報酬額に至るまで、非常にシビアに口を出してくるようになった。外国の機関投資家に対応するため、90年代以降、IRのセクションを設ける企業が増えました。経営陣と投資家のエンゲージメントがさらに深まっている今、財務上の短期的なパフォーマンスだけでなく、環境問題への対策や、途上国でのマネジメント体制まで言及してくる投資家も出てきているようです。すでにグローバル展開している企業の中には、国内外のサプライチェーンすべてにわたってCSR経営を徹底している会社もあります。今後もその動きは進んでいくでしょう。
さらに、海外ではNGOやNPOといった市民団体の力が強く、企業活動に何か問題があれば、非常に厳しく批判するなど、その影響は大きい。すでにその「洗礼」を受けた日本企業も少なくありません。そのため、電気、自動車、ITなどグローバルに展開する業界の企業は、比較的早くからCSRに取り組んできました。しかし、国内しか視野に入れずにビジネスをしてきた企業は、認識も取り組みも、まだこれからです。また、日本でもNGOやNPOが誕生して10年、まだまだ未成熟な存在ですが、市民社会の意識も変わってきました。企業不祥事などに対して厳しく見る姿勢が強くなっています。国内の状況も含め、日本企業のCSRへの対応は、ますます進んでいくことは間違いないでしょう。
── ステークホルダーと企業をつなぐために、新聞広告などのメディアに期待できる役割は。
たとえば、寄付やボランティア活動などの社会貢献活動に、CSRの一環として取り組む企業は多いのですが、これまでの日本では「社会貢献は目立たないようにやることが美徳」という風潮が強かった。しかし、社長のポケットマネーで寄付するのならばともかく、会社の資金を使っての取り組みは、本来、株主や従業員に配分されるべき資産を使っているのですから、きちんと社内・外にコミュニケーションしていく必要がある。説明責任があるのです。なぜその社会貢献活動をするのかを、幅広いステークホルダーに届くメディアを活用して説明することは、意味があることだと思います。
さらに、一般消費者は、こうした活動を伝える企業広告によって、世界で起きている環境問題や社会問題について知ることもできます。そこに、メディアの力や役割があるのではないでしょうか。
一橋大学大学院商学研究科教授
1955年大阪生まれ。1984年神戸大学大学院経営学研究科博士課程修了。経営学博士。和歌山大学経済学部教授などを経て、1997年一橋大学商学部教授。2000年から現職。2005年特定非営利活動法人ソーシャル・イノベーション・ジャパン設立、代表理事。専門は企業システム論、「企業と社会」論。最近の著書として『ソーシャル・エンタープライズ――社会的企業の台頭』(編著、中央経済社、2004年)、『CSR 企業と社会を考える』(NTT出版、2006年)などがある。

