東北新幹線「新青森開業」に伴う一連の広告を手がけた、電通のクリエーティブディレクター・髙崎卓馬さん。JR東日本「新青森開業キャンペーン」について、アイデアから企画として立体化させ、実際に広告として展開させた経緯をはじめ、広告の仕事の魅力やこだわりなどについても聞いた。
 髙崎卓馬氏
髙崎卓馬氏
――髙崎さんが所属されているコミュニケーション・デザイン・センターという部署は、電通の中でどのような役割なのでしょうか?
新商品や新サービスなどについてクライアントからオリエンテーションを受けて、クリエーティブの提案をするのが、広告づくりの一般的な流れです。私も10年以上、その枠の中で仕事をしてきました。それが、いつしか商品づくりの段階でクライアントから意見を求められたり、コンサルティング的な側面まで含め、今までより少し手前のことから相談を受けるケースが増えてきました。
私はCMプランナー出身なのですが、クライアントの悩みや思いを聞いて、ベストなソリューションを考えます。クライアントごとにいろいろなケースがあり、そういった仕事に自由な発想で回答をしていくのが、コミュニケーション・デザイン・センターです。
地元を巻き込む戦略で話題となった「新青森開業キャンペーン」
――昨年12月に開業したJR東日本「新青森開業キャンペーン」は、どのように考えていったのですか?
ミッションは新青森開業に伴い青森県が観光の目的地となるよう、他県に向けてアピールすること。そのためにも、青森県全体が盛り上がる方法を考えてほしいと相談を受けました。まずは現地の空気に触れようと青森へ行ったのですが、そのとき、青森県は他県に比べてテレビの視聴率が高いことを知りました。たとえば、全国で放送されている人気音楽番組が、青森だとなんと視聴率40パーセント超え。東京では考えられない数字なので驚きました。でも見方を変えれば、CMプランナーとしては天国みたいな場所。ここで成功できなければ、CMプランナーとしてはダメだな(笑)と、CMを中心に展開する方法を考えようと思いました。
――具体的な内容は、どのように考えたのですか?
JR東日本の「新青森開業キャンペーン」を手がける前に、NHKの大河ドラマに関する仕事をしていました。そのとき、大河ドラマがもたらす経済効果のすごさを目の当たりにしました。主人公とゆかりのある街やロケ地には多くの人が訪れ、自然発生的に地元から様々なものが生まれる。そのときの経験から、広告で大河みたいなことはできるはずだと漠然と考えていました。知ってもらうという今までの広告から少し次元の違う、人を動かすという広告のあり方をつくれるんじゃないか、と。青森の仕事を始めてすぐ自分のなかにあったひとつの仮説が現実として定着できる予感がありました。広告の対象が新発売のプロダクトではなく、青森という土地だったというのも大きいと思います。従来の方法論は通じない課題だったから。
――俳優の三浦春馬さんが駅員という設定でしたね。
東京出身の青年が青森で働きながら、地元の人や郷土料理、街などと触れ合い成長をする物語です。コンセプトは青森版『坊ちゃん』。主人公の視点を通して、青森を魅力的に見せる連続ドラマのようなCMを作りました。言ってみれば、朝ドラのような広告シリーズ。青森県民にとっても自分たちが住む街の魅力を再認識するきっかけとなり、より愛せるようになるだろうと思ったんです。とにかく、青森に住む人なら「みんな知っている」という状況を作ろうと考えました。
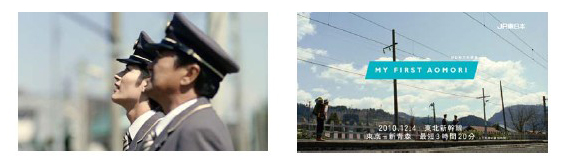
「MY FIRST AOMORI」ドラマCM
※本キャンペーンおよびテレビCMは現在終了しています。
――三浦春馬さんの相手役を一般公募したのも、地元を巻き込む戦略の一つですね。
地元の人限定で募集をしました。現場では「もし、50人くらいしか来なかったらどうしよう……」という心配の声もあったんですが、ふたを開けてみれば2,354人の方が応募してくださいました。東京でいう何万人規模と同等ですが、青森の人たちの期待値の高さを感じることができて感激しましたね。地元のテレビ局の方々も協力してくだり、オーディションの様子を番組で放送したので、より一層話題となりました。
――槇原敬之さんによるCMソングはストーリーのイメージにぴったりでした。
私が仕事をする上で欠かせないのが「音楽」です。アイデアを具体的に詰めていく過程で、企画の言語化できない部分を自分で確認する意味で、自分が思い描くテーマと重なる歌をだいたい探します。コレだと思う歌に巡り合うまで、iPodをいじり続けるんです(笑)。そして、このとき出会ったのが槇原敬之さんの「素直」という曲でした。これだ! と思ってからは企画が具体的に詰まっていくまで何度も何度も聞き続けました。このやり方は、どの仕事でも共通していますね。常に10個以上のプロジェクトが進行していますが、それぞれイメージの歌がたいだいあります。別な仕事をするときに脳のスイッチを切り替える意味でも、僕には必要なことだったりします。
新聞広告には、「開業の宣言」の役割を託す
――東京では開業間近にCMやポスターをよく見かけました。
まず青森ですべて放送や掲出をしてから、東京に持ち込みました。あえてそういう状況をつくったんです。青森のドラマが東京に、という「自分たちのもの」意識をつくりたくて。CMは湖や温泉といった観光地ではなく、心理描写できる場所を探して撮りました。そのかわり、ポスターは「行きたい」と思える、シズル感を出そうと考えました。
――具体的に、ポスターのシズル感はどのように演出したのですか?
三浦春馬さんには駅員に扮したドラマとは別に、実際に地元の人たちと触れあう機会を設けました。小規模のスタッフで青森中を取材でまわり、いい場所があると三浦春馬さんがそこを「体験」する、という構成でつくったビデオのCMシリーズもあります。新青森開業の4カ月くらい前から青森では広告のキャンペーンが始まっていたので、「あの駅員役のタレントだ!」と喜んでもらえるし、他の店では「もしかしたら、うちにも三浦春馬が来るかもしれない」なんて期待も生まれるわけです。なにより初めての体験をするライブ感は、とてもいい青森の切り取り取り方だったと思っています。今自分で見ても、行きたくなりますし。ポスターは「知らない青森の魅力」を一枚のビジュアルで表現できる観光ポスターとは一線を画す空気にもこだわって、ロケーションを決めていきました。
 2010年12月4日付 朝刊
2010年12月4日付 朝刊
――開業当日に出稿された広告は印象的でした。グラフィックデザインでこだわった部分があれば教えてください。
駅員に扮していますので、「制服姿で正面を向いて敬礼」は必須と決めていました。青森らしさを出すために唯一演出したことは、雪を降らせたことくらい。あくまでも叙情的ではなく「今日から新青森が開業します」と宣言をする広告にしました。そもそも、東京から青森を東北新幹線でつなげることは、JR東日本にとって長年の宿願。何十年もかけて歩み続けてきた結果なので、その達成感をきちんと定着させたかった。だから、開業の日の朝、新聞広告で日本全国同時に発信することで、事業にかかわった大勢の方々に対するメッセージとしても機能すると考えました。
――開業当日は、さまざまなメディアでも取り上げられましたね。
今回の新聞広告はニュースを大きく見せる手段になったと思います。広告の対象(新青森が開通すること)として我々がとらえていたことが、新聞やテレビで報道として扱われたのは、何か驚きの感覚がありました。社会にとっては、一つのインフラが完成し、便利になるわけですから当然のことなんですが。開業当日に、自分は社会的に意味のある仕事を手がけていたんだと実感しました。今までいろいろ仕事を手がけてきたけれど、そんなふうに感じたのは初めて。貴重な体験だったと思っています。
――新聞の特性についてはどう考えますか。
新聞はジャーナリズムを基本とする媒体なので、キャンペーンを組み立てるうえで他のメディアとは違った位置づけをしていますね。今回の「新青森キャンペーン」も、ニュース性の高い情報として、「いよいよ本日開業」という日付を強く意識し掲載しています。
それと、新聞は日々ニュースを追うだけでないコンテンツの「企画力」が問われる時代になっていくのではないでしょうか。新聞が発信するコンテンツが、他メディアに波及していくような流れになっていけばいいと思います。
コンテンツと広告が溶け合うようなコミュニケーションを
 髙崎卓馬氏
髙崎卓馬氏
――メディアが多様化したことで既存の広告が効きにくくなっている、という声もあります。そのことについて、どう思いますか?
「見ないコンテンツ」を作って「効果がない」というのは、なにか違う気がします。広告も今や黙っていると流れてくるものという安心の土地はなくなりつつあって、探してでも見たいか、教えたくなるか、みたいなエンターテイメントコンテンツとしての魅力をもっているかが厳しく問われている時代だと思っています。そう考えてみるとそもそも、番組、広告という線引き自体が、古いという気もしています。見ている人にとって面白いかどうかが最大の価値で、それが広告か映画かドラマか音楽かはあまり関係ないのかもしれない。自分の心を動かしてくれるものを人は見たいと思っている。ただそれだけのことだと思います。そうするとメディアの枠にとらわれて既得権のなかで表現をつくっているのはある可能性を捨てているようにも思います。もっと自由でいいかな、と。映画を見てウイスキーをショットで飲みたくなる、ってよくありますよね。画面に映すだけに終わらない、より深くて豊かな人と表現の出会いをつくる意識を、あらゆるメディアのあらゆる表現者は持つべきかなと。そう最近強く思っています。
――髙崎さんのお話から、広告にはまだ可能性があることを実感できました。今は特に震災などで沈みがちな世の中です。髙崎さんのポジティブな発想とパワフルさの源はなんですか?
実は広告に出会うまで、僕は本当に「中途半端な人間」だったんです。転校ばかりしていたせいか、何ごとも本腰を入れることに躊躇(ちゅうちょ)してしまっていたところがあって。「どうせ、また転校するし」って。だから大学に入るまで、常に足場がない感じでした。その分、いろいろな人と出会い、影響を受けてきたので、興味の範囲はかなり広くなりましたが。
好きな芝居も映画も小説も作詞も、本業ではありません。でも逆に言うとそれぞれの文化のいいところを自分という人間の中でミックスしてアウトプットできるのが最大の長所だと思ってやっています。そしてそこで学んだことは、全部僕の場合、広告に還元している。
日常生活すべてのことが、広告をつくるアイデアの種です。うれしかったこと、くやしかったこと、いじめられたことなど、心の動きすべてが使えるんです。月に何本も広告を制作しているので、その都度、自分を掘り起こしています。どんな出来事も無駄じゃない、そんな広告の仕事は天職ですね。それに、僕のやっていることは、たぶん広告の未来の一つになるんだと信じています。
――最後に読者に向けてメッセージをお願いします。
僕は思ったことは言うことにしています。黙っていると考えていないのと一緒になってしまうんです。新人の頃、人前で話すのも自分の案をほめるのも恥ずかしくて嫌でした。でも、本気で通したいと思える企画さえあれば、発言する目的が生まれて恥ずかしさが消えるんです。だからプレゼンで緊張することは、ほとんどない。たとえ3万人の前でプレゼンすることになっても、平気だと思う。でも、打ち上げで5人くらいの前で乾杯のあいさつとかは、ぜんぜんダメ。しどろもどろです(笑)。
プレゼンでは、はっきり伝えることが重要だと思います。最初が肝心。「○○ですが、どう思いますか?」と投げかけてしまったら、相手側が決定権を持つことになってしまう。だから、「私はこう思います、こうすべきだ」とはっきり伝えると誤解が生まれにくい。企画を立てる時点でぶれない核となるものがしっかりあれば、客観的に言い切ることができるんです。そしてクライアントもタレントさんもスタッフも、自分が関係してよかったと思ってもらう最終形を必ず手に入れる。そこから生まれる信頼は必ず次の可能性を広げます。それは、未来の自分にとってかけがえのない宝物になります。その繰り返しです、仕事は。
ヨーダのフィギュアで上司を思い出す

「入社したときの上司に似ているんです」と髙崎さん。新人のCMプランナーはコピーライターのもとで仕事を覚えていくのが通例だが、ヨーダ似の上司は「コピーライターに付いて仕事を覚えると、表現の仕方に偏りが出てしまうことも考えられるから」とアートディレクターのもとで新人時代を過ごすように指導。その配慮に対する感謝の気持ちを忘れないように、デスクにはこれ以外にもたくさんのヨーダグッズがあるという。
アイデアを付箋に書いて、ノートに張る

小説の連載など広告以外の仕事も手がけている。話の種となるアイデアは付箋(ふせん)に書いてノートに張る。付箋を張り替えるだけで、前の文脈を後ろと入れ替えることができる。また、話を膨らますときは、横に追加していくことも可能。その後、パソコンで完成させていく。オリジナルの情報の整理術。
電通 クリエーティブディレクター/CMプランナー
コミュニケーションデザインセンター所属。1969年福岡生まれ、早稲田大学法学部卒。2002年クリエーターオブザイヤー特別賞、2006年クリエーターオブザイヤーメダリスト、2011年クリエーターオブザイヤー。
TCCグランプリ、アドフェストグランプリ、カンヌなど国内外受賞多数。
※新聞広告を手がけるクリエーターにインタビューする、朝日新聞夕刊連載の広告特集「新聞広告仕事人」に、髙崎卓馬さんが登場しました。(全国版掲載。各本社版で、日付が異なる場合があります)


