1971年9月18日。この日、日本の国民食として愛されるようになる一つの商品が生まれた。「カップヌードル」だ。「40歳」を迎えた今年、日清食品ではこの記念すべき年を盛り上げようと、大々的なPR、プロモーションを展開している。
誕生40年を記念したイベント、キャンペーンが盛りだくさん
 佐野正作氏
佐野正作氏
誕生40年に合わせ9月17日にオープンしたのが、横浜・みなとみらい地区に設立した「カップヌードルミュージアム」。日清食品の創業者であり、カップラーメンの発明者である安藤百福氏の「クリエイティブシンキング=創造的思考」を国内外に発信し、とりわけ子どもたちにその芽を大いに伸ばしていってほしいということがコンセプト。カップヌードルがどのように生まれたのか、どんな歴史をたどってきたのかといった展示や、実際にオリジナルのカップヌードルを作れるコーナーなど、学べて遊べて体験できる施設だ。コンセプトから内外装まで、クリエーティブディレクターの佐藤可士和氏が手掛けた。そして、9月17日から19日まで、横浜、カップヌードル発祥の地である大阪府池田市、大阪・梅田の3カ所で、試食ブースや参加型のクイズ大会、CMソングを手掛けたゆかりのあるミュージシャンのライブなどが開かれ、大盛況のイベントとなった。
ウェブ上では、40年間に発売され、現在は販売されていない全商品73点を対象にした「歴代カップヌードル復活総選挙」のイベントを展開。総投票数が186万票を超えるという大活況を呈した。また、40周年を記念して作った「カップヌードルロボタイマー」のプレゼントキャンペーンを実施中。お湯を注いでからの3分間を計ってくれるとともに、その間、しゃべったり踊ったりしてくれるロボットで、抽選で1万人に当たる。同社では、100万件の応募を見込んでいるという(最終応募締め切り:2012年1月16日 当日消印有効)。
夕刊の広告枠全体を通して、開発秘話からミュージアムオープンまでを「ストーリー」で見せる
これらのイベント、キャンペーンの告知で用いたのが、新聞広告だ。9月17日付の朝日新聞夕刊で展開、1紙まるごとカップヌードルの広告が飾った。
「お伝えしたい情報がとにかくたくさんあったことが、新聞の広告枠をまるごと使いたいと考えた理由です」と、日清食品ホールディングス マーケティング本部 宣伝統括部 係長の佐野正作氏。さらにこう続ける。「カップヌードルは、年齢も性別も関係なく、文字通り老若男女に愛されている商品、ブランドです。読者層も幅広く、家庭で家族が回し読みする新聞は、幅広いカップヌードルファンにメッセージを伝えるのに最適な媒体だと考えました」
1面から始まり、2・3面はCM出演経験のある戸田恵梨香さん、永瀬正敏さんが語るカップヌードルへの思い、4面は開発秘話、その後に歴史が続き、面が進むほど新しいキャンペーンの告知になって、最後のテレビ面には未来に向けた情報発信の場でもある「カップヌードルミュージアム」を紹介……と、ストーリーが感じられる流れにした。また、全体的に商品パッケージで使われている赤を基調にし、カップヌードルの容器の上下に配された「キャタピラ」と呼ばれるゴールドの模様を配するなど、商品を想起させるようなクリエーティブで全体に統一感を持たせた。
圧巻は全30段の「復活総選挙」の広告だ。40年間で発売されたすべての味のカップヌードルを紹介。そして、この場で総選挙を勝ち抜いたトップ3を発表した。見開きページに並んだすべてのカップヌードルのビジュアルは壮観だ。さらに、トップ3の「天そば」「ブタホタテドリ ローストしょうゆ味」「スパイシーカレー」の復刻版を11月から1月にかけて3位から順次発売することもこの紙面でお披露目した。「復活総選挙」のみならず、様々な情報に多くの読者が関心を寄せたようで、17日の広告掲載直後、ブランドサイトへのアクセス数はグンと跳ね上がったという。「見開きページであれば、73商品すべてを掲載できて、これまでにどんな商品があったか、いま一度ご覧いただけると考えました」
「『お誕生日おめでとう』といったメールがたくさん寄せられましたし、ツイッターでもバースデーを祝う多くの投稿がありました。また、この日の広告を手にイベント会場やミュージアムに訪れてくれたお客さまもいて、多くの方に情報が伝わったんだと実感しました」(佐野氏)
インナー効果も見逃せない。営業からは、「得意先に見せたい」という要望が寄せられた。「40周年を盛り上げ、次に進んでいこうという社内的なモチベーションが高まった」と佐野氏は評価する。
佐野氏は、「来年以降はもちろん、来るべき50周年を見据え始めている」という。今後のコミュニケーションについてはこう語った。
「カップヌードルは、基本となる味を守りながらも、容器や具材など常に進化し続けています。コミュニケーションも同じ。身近な商品でありながら、日本発の世界ブランドというスケール感を出していくことを意識し、広告を楽しみにしてくれているファンの皆さんがワクワクするような新しいコミュニケーションを追求していきたいですね」
 2-3面
2-3面
 1面
1面
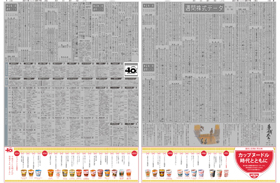 6-7面
6-7面
 4-5面
4-5面
 10-11面
10-11面
 8-9面
8-9面
 14面
14面
 12-13面
12-13面