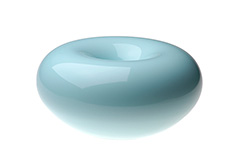「モノを作れば売れる」時代は終わった。デザインの力でできること、デザイナーに求められる役割とは? 国内外でその活動が高く評価されるデザイナーの深澤直人氏に聞いた。
今後求められるのはモノではなく、環境やシステムのデザイン
──日本のプロダクトデザインは、どのような軌跡をたどってきたのでしょうか。
 深澤直人氏
深澤直人氏
1950年代以降、高度経済成長とともに自動車や家電をはじめとするエレクトロニクス産業の技術力が急速に発達し、製品が一気に増えたときに、それを誰かがデザインする必要が出てきた。つまり、日本のプロダクトデザインは、技術とともに発達してきたのです。
それ以前の日本は、器や家具は工芸的な位置づけで、いわゆるプロダクトデザインというカテゴリーすら存在しませんでした。自動車も家電も、それを手に入れることで豊かになれると思っていた時代です。作る側は「売れるからどんどん作れ」「消費者に買ってもらうために魅力的なデザインをしろ」「専門のデザイナーに頼んでいると追いつかないから自社で雇って育てよう」となった。
こうして日本独特の「企業内デザイナー」が生まれ、プロダクトデザインを担うことになりました。デザイナーと産業構造が密接な関係を持ち始めたのです。そして、「コンシューマーエレクトロニクス」と呼ばれる個々の消費者に向けた家電製品を次々に作り、急成長した企業やブランドがたくさん生まれました。ソニーやパナソニックなどはその象徴と言えます。
──そうした変遷を経て、プロダクトデザインが置かれている現状は。
家電を例にとると、かつて「テレビ」「冷蔵庫」「エアコン」などは独立した存在で、消費者はそれらを家の中に置くことで豊かさを感じていました。部屋に置くべきモノがいっぱいあったから、その分多くのデザイナーが必要でした。
ところが技術の進歩で、例えば、壁からせり出した大きなエアコンがなくても、ホテルの空調のように快適な気温や空気を保つことができるようになりました。こうした状況が実現するようになった今、斬新なデザインを提案しても消費者の購買意欲はわかず、むしろ、ビルトインのエアコンを設備したすっきりとした部屋に住みたいと思うでしょう。モノよりも環境を求めるようになっているのです。
携帯電話を例にとると、SIMカードやSDカードだけが自分のもので、外側の端末は自分の都合で取り換えていけばいいと考えれば、自分のものという感覚ではなくなってくるはず。つまりモノの機能は利用するけれど、自分が保有するという考え方がなくなっていくというのが、これからの潮流だと思っています。とすれば、手を変え、品を変え「買いましょう、買いましょう」と盛り上げて経済成長してきた産業に付随していたプロダクトデザインは、もはや存在意義がなくなってしまう。そうした兆しが今、すでに現実になり始めているのです。
──消費者の「モノ」や「消費」への意識が変わる中、デザイナーに求められる役割、資質とは何でしょうか。
テクノロジーが進歩で消費者を取り巻く心地よい空間や環境が整いつつある一方で、以前のようにスイッチ1つで1つの機能を動かすといったわかりやすさはなくなり、モノや端末の使い方が複雑になって情報も多層化しています。そこで「人間」「環境」「モノや機能」という3要素の関係性をつなぐインタラクションデザイン、システムデザインといったスキルが求められています。実際、この作業ができるプロダクトデザイナーはすでにモノのデザインからインタラクションデザインに移行し始めています。
例えば、自動車。消費者が「保有するモノ」と考えていた時代は、自動車メーカーはいろいろな消費者のニーズに合う多くの車種を作ることが必要でした。しかし今は、交通の便のいい都会では、自動車は必要ないと考える人が少なくありません。
むしろ高齢化が進み、団塊の世代がさらに年を重ねたら、運転できない膨大な数の高齢者が、買い物や病院に行けなくなるかもしれない。高齢者を自宅から病院まで安心、安全、そして快適に運ぶために、どんな技術やシステム、サービスが必要なのか。新たな発想のインフラを、予算を含めてトータルで考える。それは、おそらくデザイナー的な思考を持った人でないとできないと思います。
僕自身、いくつかの企業のブレーンとして、経営者と話す機会を得ています。大きく移り変わる世の中で常に兆しを読み、経営者に今起きている兆しにどう対処するかアドバイスをする役割です。ある動きに対して「そうそう、私もそう思っていた」と多くの人が共感する。それが兆しです。それをいち早くキャッチするのも、デザイナーに求められるセンスと言えるでしょう。
とはいえ、兆しを読めたところで、ただ経営者とおしゃべりしていたのでは何も生まれません。デザイナーは絵を描き、造形をして、頭の中のアイデアを目に見える形にアウトプットできます。企業のトップが持つビジョンに耳を傾け、それをビジュアライズ(視覚化)、リアライズ(具現化)することで、経営者が明確に意思決定できる。それが実は、デザイナーの大きな職能だと考えます。
兆しを読み取るまではシンクタンクの研究員や広告を手掛けるグラフィックデザイナーでもできることですが、デザイナーの場合、さらにその先の具体的なデザインを提示できる。逆に言えば、我々デザイナーは「最後の線」まで引けないといけない。「embodiment(具体化)」、すなわち抽象に姿を与えることがデザイナーにとっての重要なスキルなのです。
企画やコンセプトをいい形に作り上げていくデザイナーは、企業の中にはたくさんいます。しかし、一番上流にある兆しをとらえて概念を打ち出し、最下流のデザインをするところまで全部つなげてできるデザイナーは、今の日本にはまだまだ少ないと思います。
経営者やビジネスパーソンにも求められる「デザインシンキング」
──経営者は、兆しを読むデザイナーのスキルを生かせているのでしょうか。

生かせない経営者が多いですね。そもそも、経営者自身がデザイン的なマインドや思考を持っていることが少ないので、仕方がないと言えば仕方がない。今、米国シリコンバレーから発信された「デザインシンキング」という言葉が世界中から注目されています。日本語に訳するのなら「デザイナーのごとく考えなさい」。お話ししてきたように、ビジョンをビジュアライズして考えてみろ、ということです。
このデザインシンキングを学ぶ「d.school」がスタンフォード大学に創設され、この動きは世界中に広まりました。ちなみに「d.school」を立ち上げたデビッド・ケリー氏は、私が米国のデザインコンサルタント会社のIDEOで働いていたときの上司で同社のファウンダーです。世界の多くの企業がこの考え方を採用するようになり、日本でも東大に同様の「i.school」が開設されました。
米国のIT業界などでイノベーターと呼ばれる人たちは、みなこの思考を持っていて、次々に新しいビジネスや仕組みを生み出しています。ソフトを生み出すのが米国人は得意で、アイデアひとつで一晩にして一獲千金を手にするケースも少なくありません。日本人は逆で、アイデアを考えるのは苦手だけど、そのアイデアを実際に細やかに動かしたり、動かすためのデバイスを作ったりする技術は非常に得意。ロボットや生産技術、建設やインフラを作る技術で日本にかなう国がないことは、世界中が認めています。
──改めて、深澤さんが考える「デザイン」とは。
家電でも家具でも、プロダクトデザインをするときには、そのモノを手にしたことで消費者が豊かになること、そして商品が売れて会社が潤うことまで考えて、最後の最後の1ミリまで線を引く。そこまで追い込めるのは、予測値があるからで、マーケティング的思考が必要です。
アイデアの源泉は私の中にはありません。みんなが共有している暗黙知の中にあり、その兆しを感じ取り、消費者の「こんなものが欲しかった」を具体化するのが、デザイナーとしての役割。そう考えています。
プロダクトデザイナー
1956年山梨県生まれ。80年多摩美術大学プロダクトデザイン学科卒。89年渡米、IDEO入社。96年IDEO東京支社長。2003年NAOTO FUKASAWA DESIGN 設立。卓越した造形美とシンプルに徹したデザインで、電子精密機器から家具・インテリアに至るまで幅広く手がける。米国IDEA金賞、ドイツ iF design award 金賞、日本グッドデザイン賞金賞など受賞多数。「MUJI」壁掛け式 CDプレーヤー、「±0」加湿器、「au/KDDI」INFOBAR、neonはN.Y.MOMA収蔵品。07年ロイヤルデザイナー・フォー・インダストリー (英国王室芸術協会) の称号を授与。良品計画デザインアドバイザリーボード。10 年~14年グッドデザイン賞審査委員長。多摩美術大学統合デザイン学科教授。12年7月より日本民藝館五代目館長。著書に「デザインの輪郭」(TOTO出版)、 共著書「デザインの生態学ー新しいデザインの教科書」(東京書籍)、作品集「NAOTO FUKASAWA」(Phaidon)など。