第1回「日本マーケティング大賞」が発表された。選考に携わった一橋大学大学院商学研究科教授の古川一郎氏に、全体の印象や今後の課題などについて話を聞いた。
評価、授賞することで
マーケティングの大切さを広める
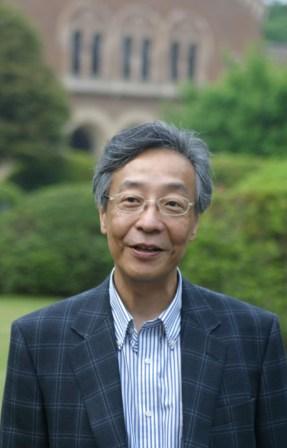 古川一郎氏
古川一郎氏
――日本マーケティング大賞の創設について、どのような印象を持ちましたか。
最初にお話をいただいたとき、これまでマーケティングを評価する賞がなかったことが意外でした。「日本マーケティング大賞」という言葉が、どこにも使われず残っていたことも驚きでしたね。いいものを作ったからといって必ずしも売れるとは限らないため、それをどう伝えていくかというマーケティング活動は非常に大切です。賞という形で評価されることで、多くの人が注目し、そこから学ぶこともできる。そういう意味では、必要な賞ができたと思います。
――選考作業はいかがでしたか?
まったく白紙からのスタートだったので、賞の選考を行った運営委員全員で、まずはどういう尺度で評価すればいいのかについて話し合いました。たとえば、特に大賞の場合、来年つぶれてしまうような会社では困るし、ある程度の人たちが納得するような会社でなければいけません。でも一方で、小さくても、今この瞬間すごく元気で輝いている、そんな企業を広く知らせたいという思いもありました。結果として、ある種「一芸に秀でた」という評価の奨励賞が設けられました。
非常に興味深かったのが、最初に上がってきたリストです。140点余りがエントリーされましたが、これは実務の現場にいる皆さんが、それぞれ注目している企業や取り組みを推薦してくれたもので、学者の私は知らないこともたくさんありました。こういう企業に注目すればいいのかと、とても勉強になりましたね。
そのリストを2回ほど選定した上で、運営委員の投票で賞を決めました。評価尺度の設定や、選定方法については、来年以降を想定しながら進めていった、という感じでした。
作り手と使い手が近いことが
「本当にほしいもの」につながる
――受賞企業について、評価を聞かせてください。
全体として言えるのは、モノづくりへの考え方がしっかりしている企業が、結果的に選ばれたことです。しっかりと使い手の声に耳を傾け、どういう商品を作るべきなのかを考えて作っている、という印象です。
大賞のファーストリテイリング(ユニクロ)の「ヒートテック」は、下着に関する私たちの印象を大きく変えました。これまでも防寒機能を持った衣類はありましたが、アウトドアなど過酷な状況を想定したもので、都会で着られるような防寒用の下着はほとんどなかった。ヒートテックは下着を機能で選ぶという新しいものの見方を、消費者の頭の中に作ったと思います。それができたのは、素材づくりからスタートし、商品開発、生産、そして販売までも、自分たちでトータルにやっているからこそ、ではないでしょうか。
昔は、モノの作り手と、その良さを伝える人と、使う人の距離が非常に近かった。しかし、現代は効率性を高めるため、どんどん分業化しています。確かに効率はよくなるかもしれませんが、作り手と使い手は離れてしまうので、使う人が何をほしがっているのかが見えにくくなっています。ユニクロは、販売の現場を持っていることで、使い手の声に応えるマーケティング活動を展開することができ、それが結果として、ブランド価値の向上にもつながっていると思います。
奨励賞を受賞したハーレーダビッドソン ジャパンは、単なる商品の魅力だけでなく、形のない「楽しさ」「ライフスタイル」を提案した点が評価されました。同社は顧客と交流するイベントに力を入れていますが、全国から3万人もが集まる大きなイベントを、外部の力に頼ることなく、企画内容から運営まですべて自分たちで行っている。使い手と直接触れ合い、声を聞くことで、顧客との強固なきずなができています。大型バイクの市場において、日本の名だたる競合企業を抑え、19年連続増収増益を続けているのは、まさにきずなの結晶なのではないでしょうか。
同じく奨励賞の、料理の「つま」をビジネスにした「いろどり」は、料亭がどのような葉っぱを求めているのかを、もともと農協の職員で、現在、代表取締役の横石知二さんが身をもって学びました。それを地元のお年寄りに伝え、お年寄りがその葉っぱを集めて収入を得ています。料亭は「使い手」、お年寄りが「作り手」ですから、いろどりから見ればやはりこれも距離が近い 。日本の多くの地域が抱える過疎化と高齢化の問題の解決の光も見える、ソーシャルマーケティングの実践が高い評価を得ました。
――来年以降の課題、展望は。
奨励賞に該当するようなおもしろい企業や取り組みがもっとリストに上がるように、マーケティングに携わる企業の方だけでなく、学識経験者などからも広く推薦してもらうことを考えていきたい。また、評価項目をもっと洗練させて、よりよいリストが整備できれば、来年以降さらに充実したものになるでしょう。
今後は、ただ賞をあげておしまいではなく、どこがよかったのかをさらに分析し、ケーススタディーとして広く伝えていきたいと考えています。



