さっとお湯に混ぜれば鮮やかに広がる色の楽しさと、湯気と共に立ちのぼるやさしい香り。銭湯から内風呂へ――。日本人のお風呂習慣の変化と共に家庭に浸透した「バスクリン」は、昨年、誕生80周年を迎えたロングセラーです。
誕生の背景や時代に合わせたマーケティング戦略の変遷、そして昨年のリニューアルの狙いなどを、商品開発部 ヘルスケア企画課課長の髙木崇氏に聞きました。
「温泉成分」と「香り」という価値は誕生時から

金森氏 私の子供の頃、入浴剤はまだぜいたく品で、「大人になって一家を構えたら、絶対毎日使ってやるぞ」と思ったものです(笑い)。「バスクリン」は昨年80周年を迎えましたが、さらにさかのぼると「中将湯(ちゅうじょうとう)」という前身の商品があったそうですね。

高木氏 「中将湯」というのは婦人薬で、16種の生薬が含有されています。ある時、社員がその製造過程で出た残りかすを家に持ち帰りお風呂に入れてみたら、とても体が温まったらしいのですね。そのうわさが広がって、1897年に「浴剤中将湯」として商品化されました。
金森氏 ロングセラーの元をたどると、なんと残りかすのリサイクルですか。
高木氏 ただこれは冬はいいのですが、夏は温まり過ぎてしまったそうです。夏用に何かできないかと考えた結果、「温泉由来のミネラル成分を使い、さらに香りをつけてみたらどうか」ということになりました。これが芳香浴剤「バスクリン」の誕生となります。

金森氏 なるほど、“生薬から温泉成分”という大きなジャンプがあり、さらに“香り”という新しい価値が誕生時からあったのですね。
高木氏 当時は松葉の香りを利用したという記録が残っています。ちなみに皆さんに親しまれているジャスミンの香りが登場したのは1960年です。
金森氏 発売当時はどのような方が買われていたのでしょうか。
高木氏 当時は内風呂のあるご家庭はまだ少なく、銭湯向けがメーンでした。
金森氏 「浴剤中将湯」の頃と同様、まだ業務用だったわけですか。とはいえ量産化のため社内体制の改革やバリューチェーンの組み直しなどもあったのでは。
高木氏 というより、戦争による資材状況の変化が大きかったようです。発売当時の「バスクリン」はブリキ缶でしたが、昭和20年代には金属の調達が難しくなり、生産が一時止まります。復活は1950年で、容器はガラス瓶でした。昭和40年代前半なると「バスクリン」の需要も急増し、ガラス瓶では追いつかなくなりました。そして1967年に、胴体は紙でふたが金属の「スパイラル缶」が登場します。当社はパッケージを自社工場で生産しています。コスト面も生産効率面も、そこでがらりと変わりました。
「家族とお風呂」という視点で切り開いた入浴剤市場
金森氏 生産が一番伸びた時期も、家庭に内風呂が普及した昭和40年代でしょうか。
高木氏 それは1980年代前半、昭和でいうと50年代前半ですね。入浴剤市場が当社のほぼ独占市場だった最後の頃ですが、ずっと強力なライバルがいなかったから伸びたとは思っていません。我々が市場を作ってきたんですね。かなりのCM投下をしていて、「家族とお風呂」いう視点で、「入浴が果たすこと」をテーマにずっと訴求してきました。
金森氏 環境の変化ということでは、1983年に花王の「バブ」が登場します。リーダー企業の前に、強烈なチャレンジャーが登場したわけですが、当時の対応はどのようなものでしたか。
高木氏 私の入社前のことですが、花王さんのアプローチは我々とはまったく違うものだったので、当社は“拍子抜け”をしたようです。「バブ」には材料を固めるという工程があり、投資コストも技術ハードルも高いのですね。ですから当社は、即対応をしていないのです。
金森氏 リーダー企業がチャレンジャーの戦略にカブして同質化を図るような手をうつのはマーケティングの定石ですが、あえてそれをしなかった。
高木氏 入浴剤の剤形には、液体、粉末、錠剤の大きく3つがあります。「バスクリン」はやはり粉末での勝負にかけようと。そして温泉ミネラル成分という当初からの価値を伸ばしていこうということになりました。その流れの中から技術革新が起こり、1985年に「日本の名湯」シリーズが生まれ、そして翌86年に世の中で初めて「濁り湯」という温泉地の情緒を再現した「日本の名湯 登別カルルス」を発売します。そこで再び売り上げが大きく伸びたんですね。
金森氏 花王は「バスクリン」を研究して、少なくともすぐ簡単には追従できないことをしてきた。「バスクリン」は自分たちのドメインを守りながら戦うことで、「日本の名湯」という新しいヒット商品が生まれた。そして当時は市場のパイがまだ伸びていたので、お互いが市場を形成することができた、ということでしょうか。
高木氏 そう言っていいいと思います、ちなみに「日本の名湯」シリーズは発売当初、「バスクリン」の冠が付いていました。知名、安心、信頼を担保するという目的で派生商品はまず「バスクリン」ブランドのアンブレラの下に置き、ある程度浸透した後に独立させたわけです。自分たちのよさにこだわったことは、結果的に成功したと思います。

髙木氏 金森氏
市場環境の変化の中、安心・自然の商品イメージを守り抜く
金森氏 商品の差別化、多様化が進んだ80年代後半以降には、広い意味での「お風呂に入れて楽しむもの」市場への関心がさらに高まったと思います。商品ラインアップやコミュニケーションの見直しがいろいろとあったと思いますが。
高木氏 商品のラインアップでかなりセグメント対応をしました。まず「バスクリン」の基本的な特長は、「温まる」「色がある」「香りがある」ですから、これらに特化した方向性。それと新たに、入浴の「肌をきれいにする」という清浄効果に注目したスキンケアという方向性が生まれました。例えば1989年には「バスクリンE」という製品を発売しましたが、これは酵素の力を使い肌の角質を落としてスベスベにするといったものです。それ以前にも夏用の「クールバスクリン」や、お子さん向けに香りを立たせた「バスクリンふろっこ」などが登場しています。
金森氏 バブル崩壊後は、消費者行動が変わったと思います。また「バブ」とは違い、形態的にも「バスクリン」を意識しながら、価格訴求で勝負をかける新たなチャレンジャーが登場してシェアに食い込んできたのもこの頃ですね。
高木氏 当時の市場の対応には反省面もあるのですが、いずれにしても「バスクリン」は対抗的な価格政策をするのではなく、入浴剤の王道をいこうと思いました。実は「バスクリン」は1999年に「自然のチカラ」という原点回帰をテーマにリニューアルをしているんです。その時にパッケージをすべて紙にして、金属とプラスチックの競合との差別化を明確にしました。バスクリンの強みは、安心のイメージであり、天然の温泉成分を使ったケミカル的ではない自然のイメージです。中身が環境にやさしいものなのだから、外側も環境へのやさしさをアピールしようと思ったわけです。
お風呂に入る意味を提案した新リニューアル
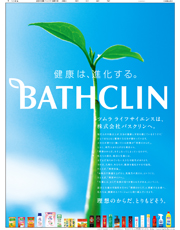 2010年9月1日付 朝刊
2010年9月1日付 朝刊
金森氏 そして昨年、髙木さんは再び「バスクリン」のリニューアルを手がけました。9月には社名も「バスクリン」に変更したわけで、大きな事業だったと思います。
高木氏 今回のリニーアルでは「自然の力」という立ち位置をもう一回決めようと。お客様に「バスクリンとは何ですか」といった素朴な質問を投げかけると、答えは「安心して使える」「楽しく使える」の2つなんです。香りがいいとか、温まるとか、こういう効用があってというのは、その2つを満たすための必須要件ではあっても、直接的に打ち出すのは違うのではないか。メッセージのこれまでの序列を変えようということになりました。具体的に私たちがとったのは「やさしい」という方向性です。これは今までのバスクリンの強みを生かすということもありますが、今の時代背景を考えると、家庭の愛を求めていると思うのですね。子供とお風呂に入りたいけれどなかなか時間がとれない。もっといえば子供とコミュニケーションがとれない親御さんも多くなっています。そういうことを「バスクリン」が解決できないかということをまず考えました。お風呂って家庭に一つのもので、小さなお子さんがいるご家庭なら一緒に入るわけですから。
 テレビCM
テレビCM
金森氏 なるほど。コミュニケーションの場としてのお風呂という、僕らの世代には懐かしい、まさに原点回帰です。
高木氏 だからお風呂に入っていただく必然性、意味を提案しようと。それが社名の変更を含め、今回の「バスクリン」の大きな提案でした。今回私たちが提案したのが「理想のからだ、とりもどそう」というメッセージです。お風呂はとにかく体が温まる。それっていいこといっぱいあるよね、と伝えようというのがファーストステップです。そして「バスクリン」なら、体がよく温まるし、安心して使ってもらえるものだ、と伝えています。また、企業「バスクリン」としても、「理想の体温、とりもどそう」というコミュニケーションを展開し、商品との両面からお風呂に入ることの意味を訴求しています。もちろんスペック的にも香りの持続性を高めるなど、さまざまな改良をしています。しかし、それをあえて強調していません。
金森氏 バスクリンって何?という原点に戻りつつ、それをより明確化したということですね。市場に転機に訪れるたび、常に根源的な価値に立ち返って考える。まさにロングセラーのあり方のひとつです。
高木氏 リニューアルというと、「私たちはここが変わりました」と声高に叫びがちです。しかし、バスクリンの本質は何も変わっていません。その本質をしっかりと伝えることが今は大切だと思っています。

バスクリン商品開発部ヘルスケア企画課課長
開発者として1999年、2010年の「バスクリン」のリニューアルを手がけたほか、「日本の名湯」シリーズの開発などにも携わった
取材を終えて
今回のインタビューで最も印象的だったのは、チャレンジャーである「バブ」に対するバスクリンの価値訴求です。製品の形態ではなく、あくまで「温泉ミネラル成分」という機能的価値と、「家族とお風呂」という体験に根ざした「安心」「楽しさ」という情緒的な価値にこだわりました。競合に攻め込まれた時、拙速に形態や特徴を模倣する例は枚挙にいとまがありません。常に自社の「本質的な価値は何か」に立ち返って、「本来の守るべきもの」を明確にし続けることが大切なのです。特に技術的な成熟度が高まっている今日、製品にまつわる無形の提供価値を守り、高めていくことがロングセラーには欠かせない条件の一つなのです。(金森 努氏)

金森 努(かなもり・つとむ)
有限会社金森マーケティング事務所取締役社長 東洋大学経営法学科卒。大手コールセンターに入社。本当の「顧客の生の声」に触れ、マーケティング・コミュニケーションの世界に魅了されてこの道20年。コンサルティング事務所、電通ワンダーマンを経て、2005年独立起業。青山学院大学経済学部非常勤講師(ベンチャー・マーケティング論)、グロービス経営大学院客員准教授(マーケティング・経営戦略)、日本消費者行動研究学会学術会員
HISTORY
1930年 バスクリン誕生
 「バスクリン」
「バスクリン」
婦人薬をつくる際の残りカスから生まれた「浴剤中将湯」が前身。商品主要成分が生薬から温泉成分へと変わり「芳香浴剤 バスクリン」が生まれた。パッケージは、大正ロマンチズムの高畠華宵氏に依頼。当時は150gで50銭と、かなり高額な商品だった。(当時の銭湯は大人5銭)
1950年 「芳香浴剤 バスクリン」ガラス瓶を発売
 「芳香浴剤 バスクリン」
「芳香浴剤 バスクリン」
 バスクリン テレビCM
バスクリン テレビCM
戦時中、資材不足により販売中止となったが、終戦から5年後にはガラス瓶で販売を再開した。
1967年 容器変更 - スパイラル缶を開発
 スパイラル缶
スパイラル缶
高度経済成長で自宅に風呂を持つ家庭が増え、需要がさらに高まった。大量消費に対応できるスパイラル缶(胴体が紙缶、上ぶたと底面がブリキ)を開発し、売上高は倍増した。
1975年 「クールバスクリン」誕生
 「クールバスクリン」
「クールバスクリン」
当時はまだ、「入浴剤は冬に使うもの」とのイメージが強かった。夏の入浴剤のパイオニアとして登場。
1984年 「バスクリン」丸缶 880gが誕生
 「バスクリン」
「バスクリン」
 テレビCM
テレビCM
大量消費の時代。
1999年 容器変更 - 人間工学に基づく持ちやすい形状/環境対応
 「バスクリン」
「バスクリン」
分別しやすく、環境へ配慮した紙容器へと変更した。紙の容器でありながら、高温多湿の環境下でも製剤が劣化しないのが特長。
2007年 「バスクリン カラダプラス」を発売
 「バスクリン カラダプラス」
「バスクリン カラダプラス」生ゆず搾りの香り(上)
新緑イオンの香り(下)
 2007年11月23日付 朝刊
2007年11月23日付 朝刊
ビタミンC配合、有機栽培によるホホバオイルなど自然派成分を使用した入浴剤。湯色は色素を使用しないビタミンB2の色。
2010年 「バスクリン」リニューアル
バスクリン誕生から80年、社名を「ツムラ ライフサイエンス株式会社」から「株式会社バスクリン」に変更。商品のバスクリンもリニューアル。天然アロマ香料を増量して香りの持続性などを向上。「ヨーロピアンローズの香り」「タンカンの香り」を新たに加えた。CMキャラクターに、女優の松下由樹を起用。
 2010年9月1日付 朝刊
2010年9月1日付 朝刊
 テレビCM
テレビCM
 「バスクリン」
「バスクリン」



