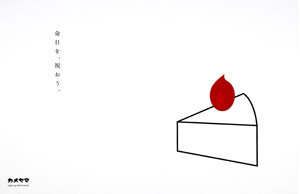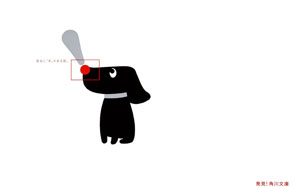多くの若き才能が集まった2011年度朝日広告賞・一般公募の部。審査委員を務めた、日本デザインセンター代表取締役で原デザイン研究所所長の原研哉氏に、作品への講評、クリエーターへのメッセージなどを聞いた。
独創性、わかりやすさ、笑い3つの要素がそろったとき、表現は見る者に届く
――朝日広告賞受賞作品について。
 原 研哉氏
原 研哉氏©Yoshiaki Tsutsui
お掃除ロボット「ルンバ」は、フローリングでも石の床でも畳でも、どんな床材でも掃除できることが、説明がなくてもよく分かります。ルンバは床に散らかったモノが障害物になると、きれいに掃除ができません。このため、ルンバがあると、掃除してきれいになるだけでなく、事前に障害物を取り除いて部屋が片付きます。そんな相乗効果の部分までが、横長のクリエーティブでうまく表現できている。隅っこにちょっとペットが顔を出しているのも、ユーモアがあります。何より、ルンバの認知度や人気が一気に高まっている今だからこそ、ルンバ本体のビジュアルが一切なくてもその性能やルンバのある暮らしが、きちんと伝わってきます。
表現は「独創性」「分かりやすさ」「笑い」の3つがうまくミックスされると、グッと人の心に入ってきます。「ルンバ」という旬な製品を表現することに独創性があり、それでいて分かりやすく、ちょっとした笑いもある。すべてがバランスよく表現できていたという点において、この作品は突き抜けていた。審査委員の満場一致で決まりました。
――準朝日広告賞を受賞した各作品についてはいかがでしょう。
「キンチョール」の法事の場面の作品。もはや定番となった「キンチョール」の広告だからこそ成立する細やかな技の冴えです。ロゴの位置もポイントになっています。「笑い」を介して伝える表現は高度。4人の人選もよくできている。
「キンチョール」のもう1作品は、伝統的商品だからこそできた表現に力がありました。シルエットだけでキンチョールだとわかるし、その性能も知っているため、ゴキブリが追い詰められている感じも理解できる。国民的プロダクツだからできた表現と言えます。手足や触覚の感じでゴキブリが観念しているのが伝わってくるし、それでいていやらしいテカリ感もあって、思わず笑ってしまいますよね。
広告というのは「理解させる芸術」。見た瞬間に頭の中で理解し、面白いと感じる。それをいかに鮮烈に行うかを競うのが、広告賞です。そういう意味では、力がある作品がそろったと思います。
広告テーマによってクリエーティブが固定しがち 新しいものがあってこそ、古いものも生きる
――今年の傾向、特徴を聞かせてください。
広告主や広告テーマが固定してきて、応募作品のクリエーティブにダイナミズムが少しなくなっているのではないか――。今年は特にそう強く感じました。
そうした中だったからこそ、大賞作品にもなった「ルンバ」が広告テーマとして加わったのは新鮮でした。ルンバが登場した当初は、「ちゃんと掃除できるの?」「どうせ故障するだろう」「すぐに電気が切れちゃうでしょ」といったふうに、世間は受け止めていました。しかし、使う人がどんどん増えて、使ったことのない人の間でも「どうやらきれいに掃除できるらしい」という期待感も強まっている。こうした面白い製品、世相、そして時代感がそろったとき、非常にユニークで、盛り上がりのあるメッセージが発信できることを実感しました。
――ほかに印象に残った作品はありますか。
個人的に好きだったのは旭化成の「サランラップ」です。桃太郎が生まれた瞬間におばあさんが桃にサランラップをかけようとしているとか、浦島太郎が玉手箱を開けたのにサランラップが張ってあって煙が出てこないといったシーンには、つい笑ってしまいます。イラストのトーンとサランラップのつやつやした描き方がいいコントラストになっていますね。
コピーで気になったのは、入選の「カメヤマ」の「命日を、祝おう」。命日というのは喪に服さなければならず、お祝いの気分とは違う慣習なのですが、それをあえて「祝おう」と言う言葉のひねりがあります。確かに、ある一定以上の年月を経た命日は、すでにお祝いであるような気がします。命日は必ずしも悲しいことではなくて、死んでしまった事実さえもだんだんハッピーなものに変わり、生きている人に希望を与えてくれる。そんな特別な日になるのは、とても幸せなことだなぁ、と。ろうそくの火をケーキのイチゴに見立てているのも、温かな気分にしてくれました。
――今回、「梶祐輔記念賞」が新設されました。
受賞作品の「国名に『本』がある国。」(角川グループパブリッシング)は、いいコピーですし、コピーライターがいかにも推しそうな作品ですが、個人的にはほんの少しだけ物足りなさを感じました。
梶さんは、確かに日本を代表するコピーライターでしたが、言葉の一発芸で広告を作る人ではなかった。広告学者でもあった梶さんは、広告への向き方がすばらしくまじめでした。たとえば代表的な仕事、トヨタ自動車の「マークⅡ・5人の会」(1976年)は、新しいマークⅡを、立場の異なる5人が様々な角度から語っていくという、非常に多層的で戦略的、コンセプチュアルな広告だった。そういったアプローチの作品を広告賞で作るのは難しいことだとは思いますが、この賞ではあえて期待したい。梶祐輔賞はいい形で育っていってほしいですね。
「広告賞」は審査委員とのコミュニケーション 世の中とのつながり方に気づける貴重な場
――次回、応募を考えているクリエーターへのメッセージをお願いします。
僕ら審査委員の役割は、「優れた作品」を選ぶことではありません。そもそも優れた作品というのは存在しない。受賞は、「今の時代だからこれを選びたい」という審査委員の意思表明、もっと言えば、クリエーターのメッセージに対する審査委員のメッセージです。つまり、「受賞」とは「審査委員といいコミュニケーションができた」ということなのです。広告はコミュニケーションです。自分がいい、面白いと思ったことを審査委員に理解してもらえたら、世の中との付き合い方が分かり、自信が持てるはず。僕自身、若いころ何度か広告賞を受賞し、表現を通じて社会と接点を持つ方法に気づき、自信になりました。広告賞に応募するということは、若きクリエーターにとって、将来につながる大きな意味があると思っています。
そして、言うまでもなく、朝日広告賞は「登竜門」です。新聞広告が好きかどうか、新聞広告をメディアとしてどう思っているか、といったことは関係ありません。「お題」を受けて、自分の才能を表現する場。チャンスの場です。才能があると信じているクリエーターは、必ず挑戦すべきでしょう。
――朝日広告賞への提言があれば聞かせてください。
今回、「ルンバ」や、辞書としては新顔の「日本語 語感の辞典」といった新しいタイプのテーマがあったことで、「キンチョール」をはじめとするおなじみの広告主、広告テーマが逆に生きた部分があったと思います。新しいものの中に伝統あるものがあるからこそ、お互いがおもしろくなる。広告賞は、テニスにたとえると、広告主がサーブを打ち、応募者がリターンを返すようなものです。それがリターンエースになるかどうかを、僕ら審査委員が評価する。リターンの技術はもちろん重要なのですが、その前に、広告主にももっと工夫のある、クリエーターを挑発するようなサーブを打ってほしい。つまり、広告主の「お題」にももっとひねりがほしい。そんな期待もしています。
原デザイン研究所所長/日本デザインセンター代表取締役/武蔵野美術大学教授
1958年生まれ。デザイナー。独自の視点から日常や人間の諸感覚に潜むデザインの可能性を提起。近年は日本の産業の潜在力を世界に提示する仕事に注力している。東京ADC賞グランプリ、毎日デザイン賞他、内外で受賞多数。2011年に北京を皮切りに個展を中国に巡回。主著に、『デザインのデザイン』(岩波書店/2003)、『日本のデザイン』(岩波書店/2011)。