写真家の石川直樹氏は、北極点から南極点への人力踏破や世界7大陸最高峰の登頂にも成功。世界最高峰のエベレストには2度登頂を果たし、世界第2位のK2の登頂にも挑戦している。国内外の辺境の地への旅を写真と映像で包括的に記録し、文章でも発表する。そんな活動を20年以上続けている石川さんの旅は、読書から始まった。

EVEREST(『広告朝日』29号表紙)
旅をしながら生きていく。高校2年の一人旅で決意
──いつから写真を撮り始めたのですか。
僕にとって写真を撮ることと、旅の始まりは一緒でした。旅と写真の親和性が高いことは、僕が言うまでもなく、みなさんも実感していることだと思います。中学2年生の冬休みに初めて一人で四国に旅をしたときも、高校2年生でインドとネパールを一人で旅したときも、当たり前のようにカメラを持って行きました。今だったらスマホで撮るんでしょうけれど。当時は、親が持っていたフィルムのコンパクトカメラで、普通に旅先で写真を撮っていました。
──旅をしながら写真を撮ることが仕事です。どのような経緯で始めたのでしょうか。
高校生のとき、インドとネパールに行ったことをきっかけに、ずっと旅をしながら生きていこうと決めました。ジャーナリストや写真家になれば、それが実現できるのではないかと幻想していたら、実際にそうなっていきました。そもそも、旅をするようになったのは、小学生の頃から読んでいた冒険や探検の本の影響が大きいです。カヌーイストの野田知佑さんや椎名誠さんなどの本を読んでいると、就職せずに旅を続けたり、あるいは会社に入ってもすぐ辞めてしまってフリーで生きている。僕もそんな風に生きていきたいと憧れました。
最初に旅に関する記事を書いたのは、高校2年生のとき。旅行会社が制作する学生向けの旅行雑誌のようなものがあって、僕はその雑誌で「高校生でもいけるインド」という連載をすることになりました。その後、20歳でアラスカのデナリに登ったのですが、その頃から自分の貯金だけでは旅の費用を賄えなくなってきた。そこで、出版社に取材費を捻出してもらおうと、簡単な企画書を書いて持っていったりしてたんです。そのとき、高校生のときに書いていた連載記事などを名刺がわりに見せたりしていました。もちろんどこの馬の骨かもわからない学生風情ですから、大半は断られましたけど、たまに面白がってくれる人もいて。最初に仕事をさせていただいたのは「ソトコト」という雑誌でした。たしか創刊号で記事を書いているはずです。
──中学生で一人旅をしたり、出版社に企画を売り込んだり、積極的ですね。
野田さんや椎名さんの本を読んでいると、なぜ旅に出ないのか、なぜ野山で遊ばないのか、と本の中から盛んに挑発してくるんです(笑)。例えば、アラスカのユーコン川をカヌーで下るのは簡単だし、こんな経験ができる目的地は他にないのだから、と強烈にあおってくる。そんな彼らの言葉に、とても影響を受けていました。
野田さんにお会いする機会があったとき、高校卒業後は大学に進学するつもりもなく、旅をしながら生きていこうと思っていると伝えました。すると、「とりあえず大学は行け」と言われたんです。アウトローの極みのような野田さんだから、「学校なんか行かず、旅に出ろ」って言われると思っていたので、逆に説得力があって、素直に従うことにしました。
──一人旅をする上で、不安はなかったですか
不安よりも、自分の判断で自由にいろんな場所に行けることの喜びのほうが大きかったですね。本に助けられたこともたくさんあります。たとえば、インドとネパールに行ったときも、汚れているガンジス川で地元の人たちは泳いだり、体を洗ったり、歯を磨いていたりする。そこに、上流から死体が流れてきたりする。かなり衝撃的な出来事なのに、さほど大騒ぎになったりしない。ほかにも、箸やスプーンなどを使わず手で食事をすることや、トイレに紙がないことも、インドの生活では当たり前ですよね。17歳の時の旅ではそういうことに一つ一つ驚いて、でもそれが嬉しくもあった。自分は確かに異文化に出会い、自分が常識だと思っていた日常から遠く離れた場所にいる、ということが本当に面白かったんですよね。旅の途上にいるんだ、と。本を読むだけではなく、ますます自分で旅をして、経験したいと思うようになりました。
登山家でも冒険家でもなく、あくまでも写真家
──写真家として本格的に活動するきっかけは。
23歳のとき、北極から南極までを1年かけて人力で走破する「Pole to Pole 2000(P2P)」というプロジェクトに参加しました。珍しい旅だったので新聞でルポを掲載しようと、朝日新聞社の写真部の方が36枚撮りのフィルムを300本くらい提供してくれたんです。
1日1本撮影するように言われたのですが、最初はなかなか36枚撮りきれませんでした。ただ、無理やり撮るうちに、撮ることが当たり前になってきた。このときが写真家体験の始まりでした。写真を多く撮ること、シャッターを切り続けることは才能の一つだと思います。たくさんのことに反応しているという証しですから。でも、結局新聞記事になったのは数回だったんじゃないかな。
ほかにも、P2Pの活動をまとめた書籍『この地球を受け継ぐ者へ 人力地球縦断プロジェクト「P2P」の全記録』(講談社)と写真集『POLE TO POLE -極圏を繋ぐ風-』(中央公論新社)を発行し、エプソンイメージングギャラリー エプサイトで写真展「石川直樹写真展 極星に向かって」も開催しました。キュレーターの方の紹介で、写真家の森山大道さんに写真を見ていただけることになったんです。そのとき、新聞社の方と森山さんが反応してくれる写真が全く違って、人によって写真の見方が全然異なるという当然のことに気づきました。その時に写真の奥深さや面白さを実感して、新聞に載るような写真を撮るというよりは、既知の世界を揺るがすような写真を撮っていきたいと考えるようになったんです。
──高所登山は登るだけでも過酷です。
過酷そうに見えますが、そうでもないんですよ。カメラを持っていけないほどでもない。持っていける時点で、そんなに大変じゃないんです。先鋭的な登山をしているわけでもないし、前人未到な冒険をしているわけでもない。登山家や冒険家が挑んでいることの、一歩手前の簡単なことしかやっていないんです。本当にすごい登山家の方々を知っているからこそ、簡単に登山家なんて名乗れません。写真家という肩書きが誇張も間違いもなく、適切です。実際、1年の大半は写真にまつわる仕事をしていますからね。
──写真と高所登山と掛け合わせた活動は、独自性があると思います。撮影する上で意識されていることは。
何でも撮ろうと思っています。テーマは決めず、自分が反応したものは全て撮る。自分が歩いた足跡をスキャンするようなつもりで、見たもの全てを記録したいと思っています。写真集や写真展のために写真をセレクトする編集作業のときには、編集者やデザイナー、他の写真家の方などに見てもらって、第三者の視点を少しだけ入れるようにしています。さきほどもお話したように、写真の見方はひとそれぞれ異なるので、できるだけ冷静に客観的に自分の写真を見たいと思っているんです。たとえば、カメラを出すのも嫌だったけど必死に撮った写真は、僕としてはセレクトしたくなる。でも、流れの中で必要なければ切り捨てる。変な思い入れなんて写真には写らないですからね。写真には見えるものしか写らない。
──旅を続ける理由は何でしょうか。
現代は分からないことがあれば、インターネットで調べて200文字くらいの説明を読むと、分かった気になったりしますよね。だけど、その場に行って身体で知覚すると、当然ですが得られる情報量が全く違います。自分の目で見て、耳で聴いて、体で感じることのほうが大事だと思っているし、また新しい別の旅にもつながっていく。旅における驚きや発見、未知の世界との出会いが面白すぎて、飽きることはありません。旅の経験や気持ちが揺さぶられた事象を、できれば誰かと分かち合いたい。それは、多くの人でなくてもいい。ほんの一握りの本当にわかってくれる人だけでも、届いてくれればありがたい。そんな思いで、本や写真集を出版したり、写真展を開催したりしています。
あと、旅の魅力は自分自身を相対化して見られることです。あらがえない自然と向き合うと、生死や運について考える機会にもなり、初心に戻ります。たとえば、水道からお腹(なか)を壊さない水が出てくることも、スーパーで新鮮でおいしい果物が買えることも有り難いと感じられる。日本の都会でずっと暮らしていると、当たり前すぎて気づかないことに感動できるんです。それは、旅をする良さの一つだと思います。
──石川さんに憧れる若者も多いと思います。最後にメッセージをお願いします。
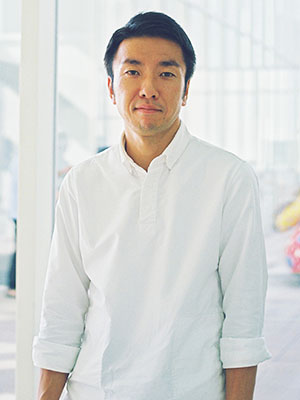 石川直樹氏
石川直樹氏
野田さんの著書「ナイル川を下ってみないか」という本の解説を書かせていただいたことがあります。その本には「ナイル川を下ってみないか。ただ、もし本当に下ったら99%お前は死ぬだろう。だけど、自分だけは応援する」というような一節があります。僕もそれと同じ気持ちです。どこを旅しても、危ないことはある。たとえ危ない目に遭って誰かがあなたを非難したとしても、僕は応援する。いろいろなことに気をつけながら、でもどんどん新しい世界に向かって一歩を踏み出せばいいと思っています。
僕はここ10年ほど、1年に1回大きな遠征に行っていました。ただ、今は新型コロナウイルスの影響で、旅に出られずにいます。日本にいる今、手がけているのは、子ども向けの絵本の制作です。ネパールの山岳民族、シェルパの男の子が主人公です。彼らが火星の山に登りに行くストーリーを温めていて。火星には標高3万メートルの山があるんです。エベレストは標高8,848メートルで、5,000メートルにあるベースキャンプから見ても、エベレストは壁のように大きかった。だから、3万メートルの山は一体どんな風に見えるのか、さまざまな資料を読みながら想像しています。生きている間に宇宙に行けたらいいな、なんて思ったりもしています。
写真家
1977年東京生まれ。東京芸術大学大学院美術研究科博士後期課程修了。人類学、民俗学などの領域に関心を持ち、辺境から都市まであらゆる場所を旅しながら、作品を発表し続けている。2011年『CORONA』(青土社)により土門拳賞、2020年『EVEREST』(CCCメディアハウス)、『まれびと』(小学館)により写真協会賞作家賞を受賞。開高健ノンフィクション賞を受賞した『最後の冒険家』(集英社)など、著書・写真集多数。